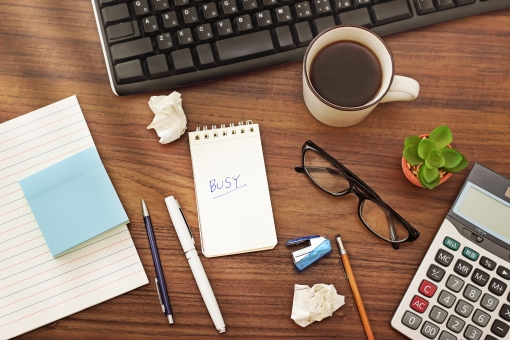こんにちは。社会保険労務士法人KESERAの原田です。
今年も最低賃金改定の時期となりました。
令和7年10月から全国で最低賃金が大幅に引き上げられ、全国加重平均は1,121円(+66円)となり、初めて全ての都道府県で時給1,000円を超える見込みとなります。
これは過去最大規模の引き上げで、物価上昇への対応や労働者の生活安定を目的としています。
最低賃金とは、法律により使用者が労働者に必ず支払わなければならない賃金の最低額のことです。
原則として、事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。
最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」がありますが、両者が重複する場合は高い方が適用されます。
なお、本社が東京にあっても福岡支店で働く従業員には福岡県の最低賃金が適用されます。
給与計算が本社で一括して行われている場合でも、事業所ごとに所在地に応じた最低賃金を確認する必要があるので注意が必要です。
ただし、一時的に本来の勤務地である都道府県以外の場所で勤務する場合は本来の勤務地のものが適用となります。
また、派遣労働者の場合は派遣先都道府県のものが適用されます。
九州地方の各県の最低賃金額は以下の通りです。
福岡県 1,057円(引き上げ額65円) 令和7年11月16日発効
佐賀県 1,030円(引き上げ額74円) 令和7年11月21日発効
長崎県 1,031円(引き上げ額78円) 令和7年12月1日発効
熊本県 1,034円(引き上げ額82円) 令和8年1月1日発効
大分県 1,035円(引き上げ額81円) 令和8年1月1日発効
宮崎県 1,023円(引き上げ額71円) 令和7年11月16日発効
鹿児島県 1,026円(引き上げ額73円) 令和7年11月1日発効
沖縄県 1,023円(引き上げ額71円) 令和7年12月1日発効
熊本県は引き上げ額が最高で、最低賃金の最高額は、東京都 1,226円(引き上げ額63円)となります。
発効日を見ると分かるように、ほぼ全国毎年10月頃発効となっていましたが、今年は11月や12月、一番遅いと令和8年3月の発効の県もあり、上昇額とともに発効日についても異例の事態となっています。
発効日が遅い場合、企業は発効日までに新しい賃金水準に対応するための準備期間を得ることができることや突然のコスト増による業績悪化やそれが原因で雇用を縮小するといった事態を防ぎ、経営の安定化と雇用機会の維持につながるメリットがあります。
令和7年は過去最高の引き上げとなりました。
政府は2020年代に全国平均で1,500円とする目標を掲げているため、これからも確認等しっかり行っていきたいと思います。